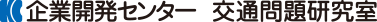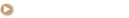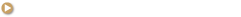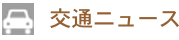2024.12.24 |
▶7割以上の人が自然災害に対して危機感を持っている ――株式会社ネクステージ 株式会社ネクステージは、全国の20歳~59歳の男女計1、075名を対象に、「車と自然災害」に関する調査を行いました。
自然災害に対する危機感についての質問では、「危機感はあるが特別なことはしていない」が34・8%で最も多くなりました。そして、「強い危機感をもち必要な備えをしている」が18・5%、「緊急性はないが、何か備えはした方が良いと感じている」が18・1%、となり、7割以上が災害に対して危機感を持っていることがわかりました。
自然災害により車に損害を受けたことがあるかという質問では、約3割が何らかの自然災害により車に損害を受けた経験がありました。その自然災害の内訳をみると、「台風」が17・0%で最も多く、「地震」が11・4%、「ヒョウ・あられ」が8・3%と続いています。
また、日々のカーライフにおいて最も恐れる事象について尋ねると、「地震」が24・1%で最多となり、「自動車事故」が22・8%で続く結果となりました。
災害により被害を受ける(受けた)際、自動車関連で最も困る、または苦労する(した)と思うことは何かと尋ねると、「車の被害額の大きさ」(23・9%)や「ガソリン不足」(13・0%)、「他の移動手段の確保」(9・1%)などの回答がありました。
所有する車について、自然災害への備えや対策を講じているかという質問では、「特に何もしていない/わからない」(64・0%)を除くと、「自動車保険の補償内容を見直した」が16・9%で最も多く、「防災グッズを車内に常備した」が16・5%で続いています。
車内に常備している防災グッズに関する質問では、「懐中電灯」が68・0%で最多となり、「簡易トイレ」が62・8%、「飲料水」が56・4%で続きました。
詳しい内容は以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000238.000010893.html
|
|
2024.12.16 |
▶6割以上の運転者がドライブレコーダーを設置している ――パイオニア株式会社 パイオニア株式会社は、車を保有・運転する全国の男女1、000名を対象に、「ドライブレコーダー利用実態、ヒヤリハットに関する調査」を実施しました。
ドライブレコーダーの設置について、63・8%が「設置している」と回答しており、同社が2022年5月に行った前回の調査と比べて9・3ポイント増加しています。
ドライブレコーダーの設置率を地方別にみると、「近畿」が71・6%で最多となり、「東海」が71・0%、「九州」が65・2%で続いています。
ドライブレコーダーと運転中の安全意識に関する質問では、75・8%が「ドライブレコーダーを設置することで安全意識が向上する」と回答しています。
運転中のヒヤリハットに関する質問では、95・9%がヒヤリハットを経験したことがあるという結果になりました。
ヒヤリハットのシチュエーションについて最も多かったのは、「歩行者や自転車の飛び出し」(64・4%)となり、「注意力が散漫していた」(49・0%)、「夜間で視界が悪かった」(35・3%)が続きました(複数回答)。
また、ヒヤリハットを経験する時間帯に関する質問では、「夕暮れ時(16時~18時)」が49・2%で最も多くなりました(複数回答)。
運転への不安に関する質問では、75・7%が不安を感じていると回答しました。
不安を感じている人に対して、どのようなときに不安を感じるかを尋ねると、「運転したことがない道路を運転するとき」が71・2%で最多となりました。そのほか、「夕暮れ時や夜間に運転するとき」(70・1%)、「慣れていない車両を運転するとき」(47・3%)などの回答がありました。
詳しい内容は以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000926.000005670.html
|
|
2024.12.09 |
▶生活道路の法定速度改正に関する意識調査 ――株式会社ウェブクルー 株式会社ウェブクルーは、2026年9月1日から施行される生活道路における法定速度引き下げ(時速30㎞)を受けて、車を所有する男女1、060名を対象に生活道路の法定速度改正に関する意識調査を実施しました。一部抜粋して紹介します。
はじめに、生活道路の法定速度引き下げについて認知しているか聞いたところ、「知っている」が38・7%、「知らない」が61・3%となりました。
生活道路を運転するときに、どんなことを意識していますかと質問したところ、「歩行者や自転車の急な飛び出し・道路横断に備えている」が68・9%で最も多く、他には、「速度を控えめにして運転している(67・1%)」、「見通しが悪い場所での徐行や一時停止を怠らないようにしている(53・5%)」などが挙げられました(複数回答)。
次に、生活道路を運転しているときに、どのくらいの頻度でヒヤリハットが起こりますかと聞いたところ、「ほとんど経験しない(年3~4回以下)」が36・4%と最も多く、「1か月に1回以上」が15・2%、「2か月~3か月に1回以上」が14・2%となりました。
具体的なヒヤリハットの経験としては、「見通しの悪い道路・交差点で自転車が飛び出してきた(47・0%)」、「見通しの悪い道路・交差点で自動車が飛び出してきた(36・8%)」などが挙げられました(複数回答)。
そして、生活道路での法定速度が時速30kmに改正されることにより、あなたの生活・意識にどのような影響がありそうか聞いたところ、「交通渋滞が増えそう(34・7%)」、「低速運転により、移動に時間がかかるようになりそう(31・6%)」などが挙がりました(複数回答)。法定速度改正後に意識したい行動としては、「出発を早めたり所要時間を多めに見積もったりして、余裕を持って移動する」が49・4%と最も多く、「混雑する時間帯を避けて移動する(45・4%)」、「できるだけ生活道路を避けたルート設定をする(24・8%)」が続きました(複数回答)。
出典:【ウェブクルー、生活道路の法定速度改正に関する意識調査を実施】生活道路の法定速度が時速30kmに引き下げ決定、ドライバーの61.3%が「知らない」という結果に(株式会社ウェブクルー)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000385.000002830.html
「ズバット 車買取比較(株式会社ウェブクルー)」https://www.zba.jp/car-kaitori/cont/column-20241031
|
|
2024.12.02 |
▶「信号機のない横断歩道」での一時停止率を公表 ――JAF JAFは、2024年8月7日~8月28日に全国で実施した「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査の結果を公開しました。
調査は各都道府県で2箇所、全国合計94箇所において、信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両6、647台を対象に実施されました。このうち、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は3、525台(53・0%)で過去最高となりました。前年に行われた同調査結果と比べると7・9ポイント増加しており、毎年増加傾向にありますが、いまだに約半数以上の車が止まっていません。
JAFは、ドライバーに対し、横断歩道を通過するとき、横断しようとする歩行者がいる場合には横断歩道の直前で一時停止することや、横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の手前で停止できるようあらかじめ速度を落とすことを呼びかけています。
また、前方を走行する車両が横断歩道で一時停止している場合、歩行者の横断を優先している可能性があることと、交通ルールでも横断歩道の手前30m以内では前方の車両を追越し・追抜きしてはいけないと定められていることから、横断歩道の手前にある標識や標示に注意して運転するように呼びかけています。
出典:「信号機のない横断歩道」まだ約半数が止まらない!JAF実態調査の結果を公表(JAF)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005512.000010088.html
|
|
2024.11.25 |
▶全国の行政処分事例を調査した結果、貨物自動車運送事業法に基づく違反が最多 ――アラームボックス株式会社 アラームボックス株式会社は、2023年9月1日~2024年8月31日に官公庁が公表した2、430件の行政処分および行政指導を対象に、根拠となった法令を調査し「行政処分件数ランキング」を集計し、その結果を発表しました。その中から運送業に関する部分を抜粋して紹介します。
ランキング結果で1位となったのは「貨物自動車運送事業法」(504件)でした。主な違反内容としては、運転者の体調や酒気帯びの有無を確認する点呼や乗務等の記録を適切に行っていない、許可された重量を超えた貨物を運搬した過積載運送などが挙がっています。
また、「道路運送法」(410件)が3位となり、主な違反内容としては、運転者の拘束時間および休日労働の限度超過や、疾病や疲労のおそれがある運転者に運行業務をさせたことなどが多く見られました。
詳しい内容は以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000024095.html |
|
2024.11.18 |
▶半数以上がシェアリングサービスの利用経験あり 利用する理由は「低コストで利用できる」が最多 ――パーク24株式会社 パーク24株式会社は、自社サービスの会員5、244名を対象に「移動関連のシェアリングサービス」に関するアンケートを実施しました。
移動関連のシェアリングサービスの利用経験が「ある」と回答した人は57%でした。利用経験ありの割合を年代別にみると、20代以下が8割以上であるのに対し、60代以上では半数を下回っており、年代による違いがみられました。
利用したことのあるシェアリングサービスは、「カーシェア」が88%で最多となり、「サイクルシェア」が23%、「駐車場シェア」が13%で続いています(複数回答)。
また、シェアリングサービスを利用した理由に関する質問では、「低コストで利用できる」が66%で最も多くなりました。そのほか、「維持費がかからない」(57%)、「自宅の近くで利用できる」(56%)、「出先・旅行先で利用できる」(35%)などが挙がりました。サービス別に見ても、全てのサービスで「低コストで利用できる」が最多となりました(複数回答)。
移動関連のシェアリングサービスの利用経験がない人に、今後どのようになったらサービスを利用するかを尋ねると、「自宅の近くで利用できるようになったら」が45%で最多となりました。そして、「今よりも低コストで利用できるようになったら」が38%、「行きたい出先・旅行先で利用できるようになったら」が35%で続いています(複数回答)。
詳しい内容は以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000695.000008705.html |
|
2024.11.11 |
▶自転車利用者・非利用者全体でヘルメット着用努力義務化の認知度は約9割だが自転車利用者のヘルメット着用率は約3割 ――全国共済農業協同組合連合会 全国共済農業協同組合連合会は、全国の男女(15歳~84歳)の"自転車利用者"と"自転車非利用者(歩行者や自動車ドライバーなど)"計22、400人を対象に、自転車の交通ルールやヘルメット着用に関する意識調査を実施しました。
改正道路交通法施行により、令和5年4月1日から年齢を問わず自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されたことを知っているか、自転車利用者・非利用者全員に質問したところ、どの年代でも80%以上の人が認知しており、全体では89・0%の認知度となりました。
次に、自転車を利用している男女11、200人に自転車乗車中にヘルメットを着用しているか質問したところ、着用している人は自転車利用者全体の26・2%でした。
自転車乗車中にヘルメットを着用しない人を対象にその理由を尋ねたところ、「非常に当てはまる」「ある程度当てはまる」の合計が最も多かったのは、「ヘルメットの着用が面倒だから」(82・8%)となりました。
また、全回答者を"ヘルメット着用者""ヘルメット非着用者""自転車に乗らない歩行者・ドライバー"の3つに分けて、ヘルメット着用率が向上するきっかけはどのような時か聞いたところ、3つとも共通して「ヘルメットの着用が義務化したとき」「ヘルメット非着用者に対して罰金刑が科せられることになったとき」「ヘルメット着用に対する取り締まりが強化したとき」などの法的環境に回答が集まりました。
詳しくは以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000149810.html |
|
2024.11.05 |
▶4分の1の事業者が「時間外労働上限規制」適用以降、「働きにくくなった」と回答 ――株式会社タイミー 株式会社タイミーが、タイミーに登録している事業者442社を対象に「物流2024年問題」についてアンケート調査を実施しました。
「物流2024年問題」への対応の度合いを質問したところ、7割近くの事業者に対応が発生していました。
対応が発生している事業者に対応状況を聞いたところ、2024年3月時点で対応完了済の事業者は35・6%、4月~8月の間に対応完了した事業者は15・8%となりました。12月までに対応完了予定の事業者は7・0%、2025年1月以降に対応完了予定の事業者は3・0%となり、残りの約4割の事業者は対応の目処が立っていないと回答しました。
次に「時間外労働上限規制」適用後の変化について質問したところ、「増えた」という回答で多かったのは「燃料・資材価格」「人件費」「作業人員」「給与」「業務量」で、「減った」という回答が多かったのは「残業時間」「荷量」「輸送距離」でした。
また、「時間外労働上限規制」適用後の働きやすさを聞いたところ、「変わらない」が67・0%で最も多かったものの、4分の1以上の事業者が「働きにくくなった」と回答しました。
詳しくは以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000036375.html |
|
2024.10.29 |
▶覆面添乗調査を実施して 貸切バスの安全運行を確保 ――国土交通省 国土交通省は、貸切バス事業者の法令遵守の状況を確認するため、監査官が営業所に立ち入る臨店監査や、観光地や空港等のバス発着場において街頭監査を実施しています。くわえて、民間の調査員が一般の利用者として実際に運行するバスに乗り込み、適切な休憩時間の確保など、監査における書面等の調査では確認できない運行実態を調査しています。
本調査は、平成29年度より実施しており、重大な法令違反の疑いが確認された事業者には監査を実施し、その結果、法令違反が確認された事業者に対して、行政処分や指導を行っています。今年度は、令和6年10月から令和7年2月にかけて無通告により実施しています。
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000663.html |
|
2024.10.21 |
▶貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正 ――国土交通省 近年、EC(電子商取引)市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大しています。それに伴い、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約5割増加しています。
この状況を踏まえ、国土交通省は貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するため、自動車事故報告規則等の一部を改正する省令等を令和6年10月1日に公布しました。
新制度の概要、施行日と経過措置については以下の通りです。
●新制度の概要
①貨物軽自動車安全管理者の選任と講習 受講の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うことを義務付け
②業務記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存を義務付け
③事故記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及びこれらの記録の3年間の保存を義務付け
④国土交通大臣への事故報告の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告を義務付け
⑤特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、特定の運転者(※)への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことを義務付け
(※)事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者
●施行日
・講習機関に係る登録関係
令和6年11月1日
・貨物軽自動車運送事業者に対する規制 関係
令和7年4月予定
●経過措置
既存の貨物軽自動車運送事業者に対する規制については、以下の猶予期間を設ける。
・貨物軽自動車安全管理者の選任:施行 後2年
・特定の運転者への特別な指導及び適性 診断の受診:施行後3年
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000665.html
|
|
2024.10.15 |
▶ベテランドライバーのクルマの装備に関する実態調査 ――株式会社KINTO 株式会社KINTOは、過去5年以内に新車を購入した運転歴10年以上のベテランドライバー550名を対象に、車の装備に関する実態調査を実施しました。調査結果の一部を抜粋して紹介します。
はじめに、車に装着している機能・装備を聞いたところ、ナビゲーションシステムが84・6%で最も多く、ほかには、ドライブレコーダー(81・0%)、自動(被害軽減)ブレーキ(75・1%)などが続きました。
実際に使用頻度の高い車の装備を聞いたところ、LEDヘッドライトが73・9%で最も多く、ドライブレコーダー(72・2%)、ナビゲーションシステム(67・7%)なども使用頻度が高い装備として回答が挙げられました。
次に、購入時は装着しなかった機能・装備を購入後につけたくなった経験の有無を聞いたところ、「かなりある」が13・8%、「ややある」が37・8%と半数以上が車を購入後に新しく機能や装備をつけたくなったと回答しました。
購入後につけたくなった具体的な機能・装備では、ドライブレコーダー(23票)が最も多く、自動(被害軽減)ブレーキ(18票)、360度カメラ(13票)などが挙げられました。
そして、運転初心者や初めて車を買う人におすすめしたい機能・装備についての質問では、自動(被害軽減)ブレーキが55・1%で最も多く、次いで、踏み間違え時サポートブレーキ(44・4%)、360度カメラ(39・6%)が挙げられました。
出典:株式会社KINTO
https://kinto-jp.com/
【運転初心者必見!新車を乗りこなすベテランドライバー550名に聞いた】初めてのクルマにおすすめの装備、第1位「自動(被害軽減)ブレーキ」(株式会社KINTO)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000054790.html
|
|
2024.10.07 |
▶冠水部分の深さがわからないとき 10・20代の約2割は対応がわからない ――ソニー損害保険株式会社 今回は、ソニー損害保険株式会社が実施した「2024年 全国カーライフ実態調査」から、一部抜粋して紹介します。
冠水部分の深さがわからないとき
約6割が進入せず引き返す
走行している道路の前方が冠水しており、冠水部分がどのくらいの深さかわからない場合どうするか聞いたところ、「進入せずにすぐに引き返す」が60・6%で最も多くなり、次いで「停止して様子をみる」が17・8%と続いています。
年代別にみると、10代・20代では「わからない」が18・0%と他の年代と比べて多くなりました。
認知度が最も低い交通違反行為は
信号待ちでの運転手の交代
提示した交通規則違反に該当する行為のなかで知っていたものを聞いたところ、最も知られていたのは「信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しない」で61・4%でした。一方で、「信号待ちのタイミングで運転手を交代する」の認知度は26・0%で最も低く、次いで「エンジンをかけっぱなしで車を離れる」が27・1%と低くなっています。
出典:「2024年 全国カーライフ実態調査」(ソニー損害保険株式会社 https://www.sonysonpo.co.jp/auto/)
https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2024/08/20240826_1.html |
|
2024.09.30 |
▶電子装置の検査が車検の項目に追加 ――国土交通省 |
|
2024.09.24 |
▶約35%の企業が、本当にアルコールチェックをしているか確認できていない ――株式会社AIoTクラウド 株式会社AIoTクラウドが、2024年6月に全国のアルコールチェック義務化対象企業の安全運転管理者1、197名に対し「アルコールチェック義務化に関する実施・運用状況調査」を実施しました。
「酒気帯び運転の確認」「記録の保管」「アルコール検知器の導入「アルコール検知器の有効保持」の4つについて、現在の対応状況を聞いたところ、いずれも約1割の企業が「できていない」と回答しました。
また、アルコールチェック義務化の対応を実際に始めて抱えている負担や課題について、約35%が「本当にアルコールチェックを実施しているか確認ができない」と回答しました。また、「直行直帰・深夜早朝の点呼など確認大変」「記録簿の管理・確認作業により管理者の業務負担が増えた」「紙/エクセル管理が大変」と回答した企業も、それぞれ約30%にのぼりました。
詳しくは、下記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000099005.html |
|
2024.09.17 |
▶チャイルドシートの使用率は過去最高となるも6歳未満の子供の5人に1人が未だ使用していない ――JAF JAF(一般社団法人日本自動車連盟)は、警察庁と合同で令和6年5月11日~5月26日の期間(調査データに不備があったため6月に再調査を一部実施)、自動車乗車中の6歳未満の子供を対象に「チャイルドシートの使用状況」と「チャイルドシートの取付け状況、着座状況」調査を全国で実施しました。
全国99箇所で実施したチャイルドシートの使用状況調査によると、6歳未満の子供全体の使用率は78・2%(前回比2・2ポイント増)で過去最高となりました。しかし、チャイルドシートの使用が義務付けられている6歳未満の子供のうち、およそ5分の1が依然としてチャイルドシートを使用していないことがわかりました。
チャイルドシートの使用率を年齢層別にみると、5歳の子供の使用率が最も低く、5歳の子供の4割以上が使用していないという結果になりました。
また、全国16箇所(8地域)で実施したチャイルドシート取付け状況調査では、乳児用・幼児用のチャイルドシートが自動車に正しく(取扱説明書通りに)取付けられていたのは69・8%で、残りの30・2%は何らかの問題で正しく取付けられていないことが判明しました。
取付け状況調査と同時に実施したチャイルドシート着座状況調査では、44・3%が正しく着座できておらず、着座状況についても課題があることがわかりました。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://jaf.link/3XruOgZ |
|
2024.09.09 |
▶バイクにドライブレコーダーを つけている人は約4割 ――株式会社バイク王&カンパニー バイク未来総研(運営:株式会社バイク王&カンパニー)は、16~69歳のバイク所有者を対象にバイク用ドライブレコーダーの装着に関するアンケート調査を行いました。
バイクを運転する際にドライブレコーダー(車体に設置するタイプ)を使用しているかという質問では約4割が「使用している」と回答しました。年齢別にみると、20~29歳はドライブレコーダーの装着率が高くなっています。しかし、年齢が上がるにつれて装着率は減少し、40歳~49歳では4割弱、50歳以上では約2割にまで落ち込んでいます。
ドライブレコーダーを装着しない理由について尋ねると、「価格が高いから」が58・5%で最も多くなりました。続いて、「装着に手間がかかるから」が29・3%、「バイクに取り付けられるスペースが無いから」が21・9%となっています。
バイク用のドライブレコーダーを使用してもよいと思う価格の上限については、「1万円未満」が28・1%で最多となりました。
バイクを運転する際にドライブレコーダーを使用した方がよいと思うかについては、「強く思う」が43・5%、「やや強く思う」が48・9%となり、あわせて9割以上を占める結果となりました。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000103319.html
出典
「バイク未来総研(運営:バイク王)調べ (https://www.8190.jp/bikelifelab/bikefuture/report/motorcycle-drive-recorder/) 」
|
|
2024.09.03 |
▶「令和5年度交通の動向」および「令和6年度交通施策」(交通政策白書)について ーー国土交通省 国土交通省は、「令和5年度交通の動向」および「令和6年度交通施策」 (交通政策白書)について公表しました。
本白書では、交通政策基本法(平成25年法律第92号)第14条第1項および第2項の規定に基づき、交通の各分野における利用状況や整備状況について示した交通の動向や、交通政策基本計画に掲げられた交通に関する施策の進捗状況や今後の取組方針を紹介しています。
本白書は下記の3部構成となっています。
●第Ⅰ部 交通の動向
交通を取り巻く社会・経済の動向、各分野の交通の輸送量・ネットワーク・交通事業の動向について整理。
●第Ⅱ部 令和5年度交通に関して講じた施策/第Ⅲ部 令和6年度交通に関して講じようとする施策
「交通政策基本計画」に盛り込まれた施策の進捗状況や今後の取組方針を整理。
「令和5年度交通の動向」及び「令和6年度交通施策」 (交通政策白書)について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000370.html |
|
2024.08.26 |
▶災害時における電動車の移動式非常用電源としての活用について ――国土交通省 |
|
2024.08.19 |
▶令和6年度「道路ふれあい月間」推進標語入選作品が決定 ――国土交通省 国土交通省は、「道路ふれあい月間」推進標語の入選作品を発表しました。
国土交通省では、毎年8月を「道路ふれあい月間」として、道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の各種活動を推進しています。その一環として、令和6年度「道路ふれあい月間」の推進標語を広く一般から募集し、全国から2、547作品の応募がありました。
応募作品のなかから、選考により「小学生の部」「中学生の部」「一般の部」の部門ごとに、最優秀賞1作品と優秀賞2作品が決定しました。
●最優秀賞
小学生の部
「「おはよう」も 「またね」もひびく つうがくろ」
鷹取 遵 さん(兵庫県 加西市立宇仁小学校)
中学生の部
「その道に 笑顔のバトンを 繋げよう」
長谷川 慶佑 さん(福島県 福島大学附属中学校)
一般の部
「渡ります 元気な命が 歩いてます」
上谷 鳴海 さん(兵庫県 神戸学院大学附属高等学校)
●優秀賞
小学生の部
「おもいやり はこぶよどうろ だいじにね」
小林 叶歩 さん(新潟県 長岡市立豊田小学校)
「駆け抜けた あの日あの子と あの道を」
塩原 結菜 さん(東京都 足立区立新田小学校)
中学生の部
「譲り合い ぺこりとお辞儀 あったかい」
森 心花 さん(兵庫県 三田市立ゆりのき台中学校)
「安全な 道路が届ける 人・物・心」
戸塚 玲佳 さん(静岡県 菊川市立菊川西中学校)
一般の部
「タッタッタ 道路も私も 上機嫌」
内田 伶音 さん(山口県 下松市)
「この子らと 共に未来を つくる道」
酒井 厚三 さん(北海道 札幌市)
出典:「渡ります 元気な命が 歩いてます」~令和6年度「道路ふれあい月間」推進標語入選作品が決定しました~(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001813.html |
|
2024.08.13 |
▶大型車の事故時における車両情報の計測・記録装置搭載について ~道路運送車両の保安基準等の一部改正~ ーー国土交通省 国土交通省は、道路運送車両の保安基準等の省令および道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正しました。
主な改正の概要は以下の通りです。
1 大型車の事故時の車両情報(加速度、ステアリング操作、衝突被害軽減ブレーキの作動状態等)を記録するために備えるEDR※1について、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、その記録性能等の要件を定めた国連基準が成立。これを踏まえ、大型車(乗車定員10人以上の乗用車及び車両総重量3.5tを超える貨物車)を対象として、令和8年12月以降の新型車より段階的に、EDRを備える※2。
※1 EDRは事故直前の加速度などの車両の挙動や装置の状態に関するデータ等を記録するものであり、車両周辺や車内の映像等を記録するドライブレコーダーとは異なる
※2 乗用車等の小型車は、すでに国連基準に適合したEDRを備えることとされている
2 (1)バス(乗車定員10人以上の乗用車)にビルトイン型(座席一体型)のチャイルドシートを備える場合には、従来のチャイルドシートと同等の乗員保護性能を確保する構造にすること等の要件を満たさなければならない。
(2)ヘッドレストを備える場合には、その座席位置にかかわらず、運転席に備えるものと同等の乗員保護性能を確保する構造にすること等の要件を満たさなければならない。
大型車に事故時の車両情報の計測・記録装置が搭載されます!
~道路運送車両の保安基準等の一部改正について~(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000305.html
|
|
2024.08.05 |
▶運転時にAIに求める情報は 「交通」「駐車場情報」「天気予報」が多い ――株式会社YAY 株式会社YAYは車を持つ20代から60代の男女1、020人を対象に「自動車とAI」に関する調査を実施しました。
まず、一人で運転中にAIから得たい情報について尋ねると、「交通情報」が70・8%で最多となり、「駐車場情報」が51・9%、「天気予報」が42・6%で続きました(複数回答)。ビジネス(出張)で運転している際にAIから得たい情報に関する質問でも「交通情報」と「駐車場情報」、「天気予報」が同じ順位となりました(複数回答)。
次に、複数名を乗せて運転する際にAIから情報が欲しいタイミングについて質問すると、「渋滞にはまったとき」が76・7%で最多となりました(複数回答)。
また、AIから提供される情報の詳細度はどれくらいが良いかを尋ねたところ、「ある程度の詳細情報まで知りたい」が59・4%で最も多くなりました。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000105253.html |
|
2024.07.29 |
▶車内に防災グッズを備えている人は3割未満 ――ズバット 車買取比較(株式会社ウェブクルー) 「ズバット」を中心とした比較サイトを展開する株式会社ウェブクルーは、車を所有する男女1、058人を対象に「運転者の防災意識に関する調査」を実施しました。
はじめに、車内に防災グッズを備えているかを質問したところ、「備えている」が28・1%で3割未満となりました。
また、車内に防災グッズを備えている人に対して、どのような防災グッズを備えているかを尋ねると、「懐中電灯」が52・9%で最も多くなり、「携帯トイレ」が52・2%、「応急処置用品」が46・1%で続いています(複数回答)。
一方、車内に防災グッズを備えていない人に対して、防災グッズを備える予定があるかを尋ねると、「備えたいが時期は未定」が60・6%、「近いうちに備える予定」が5・0%となり、6割以上の人が防災グッズを備える意向があることがわかりました。
そのほか、車に乗っているときに自然災害に遭った経験があるかという質問では、20・9%が「ある」と回答しており、被害に遭った自然災害の種類に関しては「地震」が59・3%で最多となりました。
続いて、災害に遭った経験のある人に対して、災害に遭ったときに防災グッズを備えていたか、また、備えていた場合はそれを活用できたかを尋ねると、53・4%が「備えていて活用できた」と答えました。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
出典 ズバット 車買取比較(株式会社ウェブクルー) https://www.zba.jp/car-kaitori/cont/column-20240626 |
|
2024.07.23 |
▶令和7年4月から有効期間満了日の2か月前から車検が受けられます ――国土交通省 令和7年4月1日施行の道路運送車両法施行規則の改正において、有効期間満了日の2か月前から満了日までの間に車検を受けても、有効期間は旧車検証の有効期限から2年間とすることとなりました。
現在は、有効期間満了日の1か月前から満了日までの間に車検を受けることが可能ですが、車検需要が年度末に集中するため、自動車ユーザーが整備・車検の予約が取りづらく、自動車整備士が残業・休日出勤となる問題が生じています。
車検を受けられる期間が令和7年4月より延びるものの、国土交通省では引き続き、混雑緩和のため余裕をもった予約と受検を呼びかけています。
詳しい内容は、下記URLよりご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000645.html |
|
2024.07.16 |
▶約7割が運転中の眠気で危険を感じたことがある ――株式会社しんげん 株式会社しんげんが運営する主婦向けの情報メディア「SHUFUFU(https://shufufu.net/)」は、車を運転する男女200人を対象に「運転中の睡魔」に関するアンケート調査を実施しました。
運転をしていて最も眠くなるときを聞いたところ、「長時間運転の時」が34・5%で最も多く、次いで「前日睡眠不足」32・5%、「渋滞の時」10・5%と続いています。
また、運転中の眠気によって危険を感じたことはあるか聞いたところ、約7割が「はい」と回答しました。
そのほか、運転中の強い眠気を覚ます対策で最も効果があると思うことを尋ねたところ、「車を停めて仮眠」が30・5%で最多となり、次いで「コーヒーやお茶を飲む」15・5%、「車を停めて体を動かす」11・5%と続いています。
出典 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000135215.html
SHUFUFU https://shufufu.net/
|
|
2024.07.08 |
▶交通事故の賠償に満足できた割合は4割未満 ――株式会社アシロ 株式会社アシロはポータルサイト「ベンナビ交通事故」にて、18歳以上の男女3、000人に交通事故被害に関するアンケート調査を実施しました。
はじめに、「自身もしくは家族が交通事故に巻き込まれたことがありますか」と尋ねたところ、45・8%が自身もしくは家族が、交通事故において加害者もしくは被害者として当事者になった経験があると回答しました(複数回答)。
交通事故の経験が「ある」と回答した人に、「事故があったときの事故後処理は誰に相談・お願いしましたか」と質問したところ、「自分が加入している保険会社」と回答した方が最多となり、次点で「相手方が加入している保険会社」となりました(複数回答)。
次に、「損害賠償や治療費などの金銭的な補償はしてもらえましたか」と質問したところ、69・7%が「もらえた」と回答しました(自身が交通事故の被害者となった経験がある人の内、無作為に選定した300人を対象に質問)。
金銭的な補償をしてもらえた人に、「賠償金額に満足していますか」と質問したところ、「とても満足している」、「やや満足している」と回答した方は合計で39・2%となり、補償された賠償金額については、「10万円未満」が34・4%で最多となり、次いで、「10~30万円未満」が24・9%となりました。
また、「事故後の対応でトラブルはありましたか」と質問したところ、18・7%が「あった」と回答しました。トラブルの内容としては、「加害者の謝罪がない」が最も多い回答となりました(複数回答)。
交通事故の賠償に満足できた割合は4割未満と判明!自身が交通事故被害に遭った300名を対象に事故後の処理実態を調査(株式会社アシロ)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000032382.html
出典:ベンナビ交通事故(株式会社アシロ)https://jico-pro.com/columns/421/ |
|
2024.07.02 |
▶令和6年度 豪雨・台風時の高速道路における安全・安心の確保について ――西日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社は、近年、激甚化・頻発化する集中豪雨や台風等による自然災害に対して、防災・減災を目的とした道路のり面の強化等の対策に取り組むとともに、通行規制に関する実施状況等の情報を積極的に発信し、また、集中豪雨や台風等による通行規制を解除する場合は、利用者が安全に走行できるように、点検や清掃等の作業を実施することを発表しました。
主な取組みは以下の通りです。
①お客さまへの広報
・大雨等の悪天候が予想される場合、気象会社より詳細な気象予測を入手のうえ、高速道路への影響に鑑みて、事前に通行止めの可能性について公表。この際、24時間以内に通行止めの可能性がある区間をMAP表示するとともに、予測時間を着色別に凡例表示するなど、分かりやすく情報を提供(西日本高速道路株式会社HPへ掲載)。
・災害が発生した場合は、被害の状況や復旧作業の状況、通行止めの解除見込みや解除情報等、状況に応じて、記者発表やHP及びSNSなどの広報媒体を活用のうえ、随時情報を発信。
・TVCM、ラジオ、休憩施設におけるデジタルサイネージを活用した広報や、気象予測に基づく今後の状況等について関係機関と合同記者発表を実施するなど、積極的な広報に取り組む。
②事前準備(日頃からの備え)
・災害対応のための資機材等の準備
・排水不良の未然防止のための排水設備の清掃・点検・改修等
・防災対応可能な人員・体制の強化
・出水期前防災訓練の実施や対応ノウハウを共有する会議等の実施
・関係機関との連携に関する取組み(顔の見える関係性の継続)
③西日本高速道路株式会社における災害事例と交通確保への取組み
・集中豪雨や台風の影響がある場合は、災害が発生する前の通行規制措置や災害が発生した際の速やかな通行止めを実施して、応急復旧を行い、早期の交通確保に努める。
令和6年度 豪雨・台風時の高速道路における安全・安心の確保について(西日本高速道路株式会社)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000405.000016810.html
|
|
2024.06.25 |
▶時間外労働の上限規制に対して 6割以上の企業が対応していない ――jinjer株式会社
クラウド型人事労務システムを提供しているjinjer株式会社は、計274人の人事担当者を対象に、時間外労働の上限規制が適用されて1か月が経過した時点における物流業界の実態調査を実施しました。
まず、トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制に関して、どの程度対応を進めているかという質問では、「対応を進めていない」が44・9%、「あまり対応を進めていない」が18・8%となり、6割以上の企業が法改正への対応が不十分なことがわかりました。
次に、対応を進めている企業にどれくらいの時期に対応が完了する予定か尋ねると、「対応は既に完了している」が52・5%で最も多くなりました。また、「3か月後までには対応完了予定」が22・1%、「半年後までには対応完了予定」が9・0%、「1年以内には対応完了予定」が4・9%となり、3割以上の企業が1年以内に対応完了予定という結果になりました。
続いて、具体的にどのような対応を行っているか質問したところ、「労働状況を正しく把握できる体制の構築」が63・1%で最多となりました。次いで、「採用強化を目的とした、トラックドライバーの労働条件の見直し」が56・6%、「勤怠システム、配送管理システム等のITシステムの活用」が44・7%となりました(複数回答)。
また、法改正への対応を進める上での課題について、「人手不足が加速している」や「給与の減額につながる」、「荷主の理解が進んでいない」などの声が挙がりました。
そのほか、法改正への対応にあたって、勤怠管理システムの導入を検討しているかという質問では、「取り組む予定はない」が19・1%で最も多くなり、「自社独自で開発済みである」が15・5%、「既にパッケージ型(オンプレミス)を導入している」が14・4%と続いています。
詳しい内容は下記記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000237.000089626.html
出典:jinjer株式会社
https://jinjer.co.jp/ |
|
2024.06.17 |
▶タイヤ点検の整備不良項目1位は いずれの車種も「空気圧不足」 ――一般社団法人日本自動車タイヤ協会 今回は、「4月8日タイヤの日」にちなむ活動の一環として、一般社団法人日本自動車タイヤ協会が4月4日から4月18日にかけて全国6か所で行った、タイヤ点検の結果を紹介します。
今回タイヤの点検を行った車両は、乗用車系が59台、貨物系が8台、特種車(キャンピングカー)が1台の合計68台でした。タイヤの整備不良車両は、点検台数68台中22台(不良率32%)となりました。
また、主なタイヤ整備不良の項目別内訳は、いずれの車種も「空気圧不足」が1位(乗用車系22%、貨物系63%、特種車100%)となりました。
空気圧不足は、自動車の燃費に悪影響を及ぼすだけでなく、安全走行にも影響します。そのため、一般社団法人日本自動車タイヤ協会は、今回の点検時に空気圧が不足していた場合には、その場で空気を補充しつつ、日常点検(空気圧管理)の励行を呼びかけました。
出典:2024年「4月8日タイヤの日」タイヤ点検結果(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)https://www.jatma.or.jp/docs/news_psd/news1276.pdf |
|
2024.06.11 |
▶ロードサービス救援依頼からみるお盆シーズンの車両トラブル ――JAF |
|
2024.06.04 |
▶特定原付が走っているのを危ないと感じたことがあるのは72.6% ――glafit株式会社 今回は、特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)に関する意識調査(電動パーソナルモビリティのglafit調べ)について紹介します。
■特定原付の普及に必要なのは
■「自転車通行帯が増えること」など
特定原付を知っているか聞いたところ、「知っている」が30・2%となりました。特定原付を知っている人に、特定原付の普及に必要だと感じていることを尋ねると、「新たに自転車専用通行帯が増えること」23・9%、「特定原付が手軽に購入できること」20・1%、「現在ある自転車専用通行帯の幅が広がること」17・9%、「特定原付の良いイメージが広がること」16・2%、「特定原付のシェアサイクルポートが身近にできること」13・4%、「特定原付のシェアサイクルポートが電動自転車同様に増えること」12・5%となりました。
そのほか、自動車を運転していて特定原付を見かける人は、「定期的に見かける」「時々見かける」を合わせて26・2%となりました。特定原付を「見かける」と回答した人に特定原付が走っているのを危ないと感じたことがあるか質問したところ、「時々ある」が最も多く40・8%となり、次いで「何回もある」31・8%が続いています。
出典:特定小型原動機付自転車に関する認知度をはじめとした意識調査(glafit株式会社)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000031007.html |
|
2024.05.28 |
▶ 春の全国交通安全運動期間における交通事故の発生状況を発表 ――警察庁 警察庁は、春の全国交通安全運動期間中(令和6年4月6日~15日)における交通事故の発生状況を発表しました。
本年の春の全国交通安全運動は、「こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践」、「歩行者優先意識の徹底と『思いやり・ゆずり合い』運転の励行」および「自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守」を全国重点として行われました。
期間中の交通事故による死者数は55人で、前年同期と比べて、6人減少(9・8%減)となりました。
年齢層別死者数では、65歳以上が33人で最も多く、全体の60・0%を占めています。
状態別死者数では、自動車乗車中が24人で最も多く、全体の43・6%を占めています。
出典:「令和6年春の全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況」(警察庁)https://www.npa.go.jp/news/release/2024/20240416harukou.html |
|
2024.05.21 |
▶バス車内事故防止のための啓発動画を公開 ――国土交通省 乗合バスにおける事故のうち、約3割は車内事故によるものとされています。車内事故による負傷者は高齢者が多く、負傷により寝たきりの生活になる高齢者も確認されています。
国土交通省では、令和7年に車内事故を85件以下とする目標を掲げており、バス車内事故の危険性をわかりやすく紹介する動画を作成しました。適切な行動の啓発のために、乗客・一般ドライバー・バス運転者に向けてそれぞれ動画を作成しています。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000161.html |
|
2024.05.15 |
▶連続運転時間は「3時間未満」と約半数が回答 ――株式会社NEXER 株式会社NEXERは、グーネット中古車と共同で、普段車の運転をする全国の男女1、000人を対象に「渋滞時の工夫」に関するアンケートを実施しました。
長時間ドライブをする際に、何時間連続で運転できるかという質問では、「2~3時間未満」が28・9%で最多となりました。全体でみると、54・1%が「3時間未満」と回答しています。
また、長時間ドライブをする際に工夫していることはあるかという質問では、46・4%が「ある」と回答しました。具体的にどのような工夫をしているかを尋ねたところ、「サービスエリアでこまめに休憩している」、「リラックスした姿勢で運転する、腰にクッションを入れる」、「お気に入りやノリの良い音楽を聞きながら運転する。甘い飲み物やお菓子を用意して疲れないようにする」などの声がありました。
そのほか、渋滞に巻き込まれた際に工夫していることはあるかという質問に対して、24・5%が「ある」と回答しており、具体的にどのような工夫をしているかを尋ねると、「最も左の車線に居続けること」、「渋滞に巻き込まれないように時間を確認する」、「ラジオをきく」、「眠くならないようにコーヒーを飲んだり、ガムをかんだりする」などが挙げられました。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001120.000044800.html
出典
株式会社NEXER
https://www.nexer.co.jp
グーネット中古車
https://www.goo-net.com/ |
|
2024.05.09 |
▶二輪車の制動や旋回の特性を検証速度や路面の状態によって変化あり ――JAF 2023年の二輪車(原付も含む)乗車中の死者数は498人となり、2022年よりも増加しました。事故を未然に防ぐためには二輪車の特徴を把握することが大切です。そこでJAFは、二輪車の排気量別(小型二輪、普通二輪、大型二輪にくわえて検証には四輪も使用)に制動や旋回の特性を検証し、その結果を公表しました。
まず、速度と路面による制動距離の違いを検証するため、スタート地点から時速40㎞、時速60㎞、時速100㎞の一定速度で走行し、パイロンを通過後、フルブレーキを行い、ドライとウェット路面のそれぞれで制動距離を測定しました。その結果、すべての車両がドライ路面よりもウェット路面では制動距離が長くなりました。
次に、速度による回転半径の違いについて検証を行うため、スタート地点から時速40㎞、時速60㎞、時速80㎞、時速100㎞の一定速度で走行し、パイロンで作られたコースでカーブの軌跡を測定しました。
その結果、速度が上がるにつれて回転半径が大きくなり、時速60㎞と時速80㎞の普通二輪・大型二輪を比較すると2倍以上の差が見られ、時速80㎞以上では旋回時に大きく膨らむ傾向が明らかになりました。
※小型二輪は法定速度が時速60㎞のため、時速80㎞以上のテストは実施していません
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005076.000010088.html |
|
2024.05.07 |
▶電気自動車の適切な充電方法等のポイントを動画で公開 ――国土交通省 |
|
2024.04.15 |
▶ヘルメット着用を支持する意見が約8割 しかし、ヘルメットの着用率は未だ低迷 ――株式会社スコープ 株式会社スコープは、「日々のお買い物で自転車を利用している」20代から70代の女性300人を対象に自転車ヘルメット着用の意識や実態、買い物への影響についてアンケート調査を行いました。
「自転車ヘルメット着用努力義務化に対する考え」について聞いたところ、83・3%が事故防止のためにヘルメットの着用努力義務化は必要だと思っています。さらに、79・3%がヘルメットの着用は社会的責任の一つであると回答しました。
その一方で、「努力義務」なので実際はヘルメットを着用しない人が多いと感じている人が79・0%となりました。実際に、自転車ヘルメット着用努力義務化を認知している人は9割を超えていますが、ヘルメットの着用率は約2割となっています。
また、「ヘルメットを着用した時の自分自身の恰好(見た目)が気になる」や「ヘルメットを着用した時(外した時)の髪型が気になる」がともに約6割となりました。くわえて、約6割がヘルメット選びに迷い、約半数が持ち運びや盗難の心配をしており、着用率が伸び悩む原因になっていると考えられます。
そのほか、「周りがヘルメットを着用するか気になる」(69・6%)や「ヘルメットを着用しなければいけないプレッシャーを感じる」(63・0%)など、他人の着用状況に目を向ける人も多くなっています。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000060036.html |
|
2024.03.05 |
▶トラックGメンによる「集中監視月間」の取組結果 ――国土交通省 国土交通省は、令和5年11月と12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化しました。
このなかで、トラック事業者への全数調査やトラックGメンによる関係省庁と連携したヒアリング等により入手した情報に基づき、164件の「要請」と47件の「働きかけ」を実施し、違反行為の早急な是正を促し、改善計画の提出を指示しました。
また、既に「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた者には、要請後もなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があるとし、当該荷主等に対して違反原因行為をしないよう「勧告」するとともにその旨を「公表」しました。
今回「勧告」「要請」等の対象になった荷主等についても、今後の取組状況等については、トラックGメンによるヒアリングや現地訪問等を通じてフォローアップを行い、「要請」後もなお改善が図られず、違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めた場合には、当該荷主等に対し「勧告・公表」を含む厳正な対応を実施するとしています。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000292.html |
|
2024.02.13 |
▶保安基準に適合した電動キックボード等の購入・使用について ――国土交通省 国土交通省は、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等/以下特定原付)の普及を図るため、保安基準適合性を確認する「性能等確認制度」を令和4年12月に創設しました。加えて、今般、インターネットを中心に流通している81車種のうち、とくに保安基準に適合しないおそれがある10車種(10台)に対し保安基準適合性の調査を実施した結果、6車種の不適合が確認されました。
国土交通省では、保安基準適合に向けて自主的に対応していない車両の製造・販売事業者に対し指導をするとともに、保安基準不適合車両をオンラインマーケットプレイスから削除しました。また、調査未実施となっている車両についても、引き続き、性能等確認や市場調査を行うとしています。
特定原付を購入・使用する人に対しては、保安基準不適合品に注意し、商品説明欄に「公道走行不可」等の記載がないかを確認するよう呼びかけています。
なお、保安基準適合性が確認された特定原付の車種一覧や、不適合品の情報提供窓口は下記URLにてご確認ください
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
出典:「保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう!」国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000477.html
|
|
2024.01.15 |
▶「信号機のない横断歩道」での一時停止率を公表 ――JAF JAFは、全国で実施した「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査の結果を公開しました。
調査は各都道府県で2箇所、全国合計94箇所において、信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両7、087台を対象に実施されました。このうち、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は3、193台(45・1%)で過去最高となりました。前年に行われた同調査結果と比べると5・3ポイント増加しており、毎年増加傾向にありますが、いまだに約半数以上の車が止まっていません。
JAFは、ドライバーに対し、横断歩道を通過するとき、横断しようとする歩行者がいる場合には横断歩道の直前で一時停止することや、横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の手前で停止できるようあらかじめ速度を落とすことを呼びかけています。
また、前方を走行する車両が横断歩道で一時停止している場合、歩行者の横断を優先している可能性があることと、交通ルールでも横断歩道の手前30m以内では前方の車両を追越し・追抜きしてはいけないと定められていることから、横断歩道の手前にある標識や標示に注意して運転するように呼びかけています。
出典:「信号機のない横断歩道」まだ半数以上が止まらない!JAF実態調査の結果を公表(JAF)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000823.000003128.html |
|