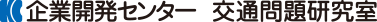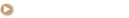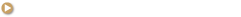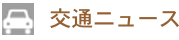2025.12.23 |
▶貨物自動車運送事業法の一部改正 違法な「白トラ」への規制を強化 ――国土交通省 国土交通省は、令和7年6月に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」のうち、違法な白ナンバーのトラック(以下「白トラ」)に係る荷主等への規制や委託次数の制限等に関する規定の施行期日を、令和8年4月1日と定める政令等が閣議決定されたことを発表しました。
これに伴い、荷主等が、白トラで有償貨物運送を行う者に運送委託を行った場合、新たに処罰の対象となります。また、荷主等が違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができるようになります。
加えて、
・再委託の回数を2回以内までに制限する努力義務
・運送契約締結時の書面交付義務等の規定(現行では貨物自動車運送事業者のみに課されているが、新たに貨物利用運送事業者にも課される)
といったところも定められます。
詳しい内容は下記URLよりご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html |
|
2025.12.16 |
▶働き方改革推進に関する相談窓口を開設 ――厚生労働省 2024年4月1日から、自動車運転業務にも時間外労働の上限規制が適用されています。また、トラック運転者の改正改善基準告示が適用されており、拘束時間についても基準が厳しくなっています。
こうしたことから、トラック運転者の働き方改革は事業者にとって速やかに取り組んでいかなければならない課題となっています。
そこで、厚生労働省では、トラック運転者の長時間労働改善のための専門の相談窓口を開設しています。
社労士等の労務管理の専門家が労働時間の上限規制への対応や同一労働同一賃金の実現など、「働き方改革」に取り組む中小企業・小規模事業者を訪問して、解決に向けてサポートします。
相談窓口は全国各地に設けられています。
詳しい内容は、下記URLよりご確認ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/ |
|
2025.12.08 |
▶遠隔点呼・自動点呼に関する 「解説パンフレット」を公開 ――国土交通省 |
|
2025.12.01 |
▶配達員の7割超が置き配を 「非常に便利」だと回答 ――株式会社ライナフ 株式会社ライナフは、全国の軽貨物ドライバー150人を対象に、置き配に関する意識調査を実施しました。
1日のうち、置き配を行う割合はどのくらいかという質問では、「ほとんど(7割以上)が置き配」が35・3%で最多となりました。次いで、「半分程度(4~6割)が置き配」が29・3%、「一部(2~3割)のみ置き配」が22・7%となり、置き配が現場での一般的な配達手段として定着しつつあることがわかりました。
置き配に関する全体的な印象については、「非常に便利だと思う」が76・7%を占めました。
置き配の活用による時間短縮効果に関して尋ねると、「1時間以上短縮できている」が44・7%で最も多く、「30分~1時間程度短縮できている」が44・0%で続いています。
また、置き配の指定が増えた場合のメリットに関する質問では、「再配達が減る」が最多となりました。そのほか、「対面時間が不要になり時間短縮になる」「自分自身のストレスが減る」「配送ルートが効率的に組める」などの声が挙がっています(複数回答)。
置き配がより広く普及するべきだと思うかについては、「強くそう思う」「ややそう思う」を合わせて9割以上が置き配の普及を期待する結果となりました。
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000015549.html |
|
2025.11.25 |
▶災害時の即応支援チーム「JAF-FAST」を新設 ――JAF(一般社団法人日本自動車連盟) JAFは、これまで全国で発生する自然災害に「JAFロードサービス特別支援隊」を派遣し、復旧支援活動に取り組んできました。近年各地で災害が頻発していることを受け、より迅速かつ的確な復旧支援を行うため、JAFロードサービス特別支援隊の組織内に災害対応の即応部隊「JAF-FAST(ジャフファスト)」を新設しました。JAF-FASTは、被災地の現場状況を迅速に把握し、必要な作業車や資機材の判断、優先すべき作業の選定を行うことで、後続部隊の円滑な活動を支援します。
●災害支援車の主な搭載装備
・発電機、照明、浄水機器などの緊急用資機材
・食料、飲料水、簡易トイレなどの生活必需品
・携帯電波圏外でも隊員間が通信可能な情報伝達装置
●期待される効果
・災害発生から12時間以内の現地入りを目指し、被害状況を即時把握
・緊急交通路確保に向けた車両の排除や、救援作業を先行実施
・現地での情報収集と共有により後続部隊の効率的な活動を支援
・JAFの全国ネットワークを生かし、より早期の地域復旧を実現
詳しい内容は、下記URLにてご確認ください。
https://jaf.or.jp/common/news/2025/20251105-001?__lt__cid=c724686c-e7d0-4b47-9d89-01eb3c1efc3d |
|
2025.11.18 |
▶最も「うっかり違反してしまいそう」な交通ルールは 「後部座席のシートベルト着用義務」 ――全国共済農業協同組合連合会 全国共済農業協同組合連合会は、2025年秋の全国交通安全運動にあわせて全国の20~69歳の運転経験者500名を対象に、「うっかり違反してしまいそう」と感じる交通ルールについて調査しました。
その結果、「後部座席のシートベルト着用義務」が最も多く24・8%となりました。次いで「泥はね運転」が24・6%、「ハイヒールなど不安定な履物での運転」が19・6%となっています。
●ベテラン層では「後部座席のシートベ ルト着用義務」が最も多い
運転歴に応じて調査対象者を「ベテラン層:免許保有20年以上」「中堅層:免許保有4~19年」「ビギナー層:免許保有1~3年」と定義して比較した結果、ベテラン層で最も回答が多かった「後部座席のシートベルト着用義務」(29・5%)は、中堅層では22・5%、ビギナー層では20・0%となっており、運転歴が長いほど回答率が上昇しました。
また、ビギナー層で最も回答が多かった「泥はね運転」(28・0%)は、中堅層では26・0%、ベテラン層では21・5%となっており、運転歴が短いほど回答率が上昇しました。そのほかの交通ルールで運転歴が短いほど回答が多かったものは、「乗合自動車発進妨害」(ビギナー層:16・0%、中堅層:8・5%、ベテラン層:8・0%)、「緊急車両への進路譲り」(ビギナー層:12・0%、中堅層:4・5%、ベテラン層:2・0%)でした。
●ほとんど運転しない層では周囲への配 慮が必要な場面での違反リスクが高い
「毎日運転する層」「ほとんど運転しない層」という運転頻度で「うっかり違反してしまいそう」な項目を比較したところ、「ほとんど運転しない層」では「泥はね運転」(30・7%)や「乗合自動車発進妨害」(18・7%)など、周囲への配慮が必要な場面での交通ルールについて、うっかり違反するリスクが高いことがわかりました。
一方、「毎日運転する層」では、「ハイヒールなど不安定な履物での運転」(23・8%)や「スマホのながら運転」(22・2%)など、「つい」やってしまいがちな違反のリスクが高い傾向にあることがわかりました。
最後に、「交通ルールを改めて学び直したいか」と質問したところ、全体の約7割が「そう思う」と回答しました(「とてもそう思う」「ややそう思う」の合計)。
詳しい内容は、下記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000051085.html |
|
2025.11.10 |
▶貸切バス事業者の法令遵守を確認する覆面添乗調査を実施 ――国土交通省 国土交通省は、貸切バス事業者の法令遵守の状況を確認するため、監査官が営業所に立ち入る臨店監査や、観光地や空港等のバス発着場において街頭監査を実施しています。
くわえて、民間の調査員が一般の利用者として実際に運行するバスに乗り込み、適切な休憩時間の確保など、監査における書面等の調査では確認できない運行実態を調査しています。本調査は、平成29年度より実施しており、重大な法令違反の疑いが確認された事業者には監査を実施し、その結果、法令違反が確認された事業者に対して、行政処分や指導を行っています。今年度は、令和7年10月から令和8年2月にかけて無通告により実施しています。
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000727.html |
|
2025.11.04 |
▶自転車への青切符導入にあたり 「自転車ルールブック」を作成 ――警察庁 警察庁は、「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)を作成しました。
自転車ルールブックは、自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入にあたり、自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方について周知を行い、自転車の安全・安心な利用を図るための資料として、警察庁のホームページで公表されています。
自転車ルールブックの構成は以下の通りです。
① 自転車への青切符の導入の背景と手続(導入の背景、検挙後の手続の変更点、青切符の対象とならない場合)
② 自転車の基本的な交通ルール(自転車安全利用五則の紹介)
③ 自転車の交通違反の指導取締り(基本的な考え方、指導取締りを重点的に行う場所・時間帯)
④ 青切符以外に自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分(自転 車運転者講習、運転免許の停止)
⑤自転車の交通ルール
詳しい内容は、下記のURLにてご確認ください。
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250902001.html |
|
2025.10.27 |
▶チャイルドシート使用状況全国調査を実施 6歳未満のこども全体の使用率が8割超 ――一般社団法人日本自動車連盟 (一社)日本自動車連盟(JAF)は、警察庁と合同で2025年5月10日~6月14日の期間、自動車乗車中の6歳未満のこどもを対象に「チャイルドシートの使用状況」と「チャイルドシートの取付け状況、着座状況」の調査を実施しました。
はじめに、全国99箇所で実施したチャイルドシート使用状況の調査結果をみると、6歳未満のこども全体の使用率は82・4%(前回調査比4・2ポイント増)で過去最高となりました。
一方で、チャイルドシートの使用が義務付けられている6歳未満のこどものうち、およそ6分の1が依然としてチャイルドシートを使用していないこともわかりました。
また、全国16箇所(8地域)で実施したチャイルドシート取付け状況調査では、乳児用・幼児用のチャイルドシートが自動車に正しく(取扱説明書通りに)取付けられていたのは74・8%で、残りの25・2%は何らかの問題で正しく取付けられていないことが明らかになりました。同時に実施したチャイルドシート着座状況調査では、44・4%が正しく着座できていませんでした。
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006349.000010088.html |
|
2025.10.20 |
▶年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施 ――公益社団法人全日本トラック協会 (公社)全日本トラック協会は、国土交通省物流・自動車局長より令和7年12月10日から令和8年1月10日までを実施期間とする「令和7年度年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施について」の通知があったことを踏まえ、輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始に臨み、自主点検等を通じた安全性の向上と輸送安全等に対する意識の高揚を図るため、年末年始の輸送等に関する安全総点検を実施します。
自然災害により事業者自身が被災し運休が生じる事案やテロ対策等、早急かつ適切な対応が求められていることから、国土交通省全体の4つの重点点検事項にくわえ、7つの物流・自動車局(自動車交通関係)重点点検事項が定められています。
点検事項については以下の通りです。
【国土交通省全体】
①安全管理(特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導監督体制)の実施状況
②自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況
③サイバー空間を含むテロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の通報・連絡・指示 体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況
④新型インフルエンザ等の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実施状況
【物流・自動車局(自動車交通関係)】
※トラック運送事業関係は②~⑥
①軽井沢スキーバス事故を踏まえた貸切バスの安全対策の実施状況
②健康管理体制の状況
③運転者に過労運転を行わせないための安全対策の実施状況
④運転者に飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況
⑤車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況(特に大型自動車の車輪脱 落事故防止対策及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況)
⑥大雪に対する輸送の安全確保の実施状況
⑦貨物軽自動車運送事業における安全対策の実施状況
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://jta.or.jp/member/anzen/anzen_soutenken2025.html |
|
2025.10.14 |
▶事業用自動車事故調査報告書 啓発コンテンツを公開 ――国土交通省 国土交通省が、公益財団法人交通事故総合分析センター(以下、イタルダ)を事務局として設置している「事業用自動車事故調査委員会」は、調査報告書をわかりやすくまとめた啓発コンテンツを作成し、令和7年1月と3月に運送事業者関係団体等に配布しました。
この啓発コンテンツのうち再配布要望など大きな反響があったものを、「事業用自動車事故調査委員会10年総括」にある「再発防止策の浸透策」の一環としてイタルダのホームページに以下の通り公開しました。
【掲載概要】
●掲載先
イタルダホームページ 事業用自動車 事故調査委員会
https://www.itarda.or.jp/commercial_vehicle_accident
●掲載内容
①啓発マンガ
THE CASE STUDY その時ドライバーに何が起こったのか
第一弾(令和7年1月発行)
貸切バスの横転事故(静岡県小山町) 令和4年10月発生 他2事案
第二弾(令和7年3月発行)
中型トラックの追突事故(山形県東 根市)令和3年10月発生 他2事案
②啓発動画
大型乗合バスの追突事故(北九州市 小倉北区)令和3年8月発生 他2事案
なお、この啓発コンテンツはスマートフォン等からも確認することができます。
詳しい内容は、下記URLにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000722.html |
|
2025.09.22 |
▶自賠責制度の重要性や役割等を紹介する ポスター・リーフレットを作成 ――国土交通省 |
|
2025.09.16 |
▶年齢や健康起因による事故防止に向けて事業用自動車事故調査報告書を公表 ――公益財団法人交通事故総合分析センター 事業用自動車の重大事故の原因を調査・分析し、有識者からの提言により事故の再発防止を図ることを目的として設置された、国土交通省の外部委託組織である事業用自動車事故調査委員会は、2022年12月2日に大阪市淀川区で発生したタクシーの追突事故に関する調査報告書を公表しました。
本事故は「重要調査対象事故」に該当し、事故原因が事業者の組織的・構造的な問題に起因する可能性があり、同種事故の多発が予測され、早期に有効な再発防止策が必要であることなどを勘案し、事故調査委員会による要因分析および再発防止策の提言が必要であると判断されました。
●事故概要
大阪市淀川区の府道41号線の三津屋跨線橋付近を十三駅方面に向けて空車で 運行していたタクシーが、前を走る大 型乗合バスに追突した。この事故により、タクシーの運転者が死亡し、大型乗合バスの運転者も軽傷を負った。
●事故原因
・漫然運転による前方不注視とペダルの踏み間違いおよび不適切なシートべルトの装着
・指導・監督体制の不備による安全意識欠如
●再発防止策
①適切な運行管理
・事業者自らが法令遵守や安全最優先の原則を徹底する
・視力の低下や視力障害などの疾患が、運転上大きな危険をはらんでいる旨を認識し、運転者が適切な運転状況にあること を確認する
②適切な指導監督
・高齢運転者については、身体的・心理的特性の変化が運転に多大な影響を与えることを認識させる事故事例の紹介など理解促進の手法を工夫して指導する
・運転者本人が意図しない装置の誤操作は、漫然運転の結果として発生するため、注意力の維持や集中力の低下を最低限に止めることが必要であると強く指導する
・日頃から運転者との良好なコミュニケーションの体制を維持し、状況を見極めながら、専門医への受診等を指導するなど適切な健康管理を行っていく
・シートベルトの適切な装着の必要性と正しい装着方法について指導を徹底する
・適性診断を定期的に受診させ、運転特性を理解させることにより、安全な運転方法を自ら考え、実践するよう指導する
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000151225.html
※国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000724.html |
|
2025.09.08 |
▶自動点呼機器・DX導入促進助成事業を実施 ――公益社団法人全日本トラック協会 全日本トラック協会は、中小トラック運送事業者における安全確保の根幹を成す運行管理について、安全性の向上や労働環境の改善、人手不足の解消等に資するため、会員事業者が自動点呼機器を導入する場合の費用を一部助成支援しています。
令和7年8月8日より、自動点呼機器の範囲が拡大(業務前自動点呼機器の開始)されたことを踏まえ、助成対象の範囲が一部改正されています。
概要は次のとおりです。
●助成対象者
各都道府県トラック協会の会員事業者で、中小事業者を対象
●助成要件
助成対象とする自動点呼機器は、国土交通省の認定を受けたもので、令和7年4月1日以降に契約もしくは利用開始したもの
●助成額
対象となる自動点呼機器の導入費用(周辺機器、セットアップ費用及び契約期間中のサービス利用料を含む。上限10万円)
詳しい内容は、下記URLにてご確認ください。
https://jta.or.jp/member/shien/tenko2025.html |
|
2025.09.01 |
▶「ドライバーの押さえておきたいヘルスケアポイント」についての動画を公開 ――公益社団法人全日本トラック協会
全日本トラック協会は、トラックドライバーの健康増進に向けた取組みを推進するため、動画によるドライバー教育など実効性のある対策を実施しています。
令和7年度は「ドライバーの押さえておきたいヘルスケアポイント」として、運動や睡眠などについての動画が全8回作成される予定です。
その第1段として、「第1回トラックドライバーのための運動習慣(基礎編)-運動のメリットと個性にあった運動のすすめ-」が公開されました。
ドライバーが視聴することはもちろん、ドライバーの健康管理、また運行管理の教育用ツールとしての活用を見込んでいるとのことです。
詳しい内容は、下記URLにてご確認ください。
https://jta.or.jp/member/rodo/kenko_top/movie2025.html
|
|
2025.08.25 |
▶運転者の健康づくりのための啓発チラシを作成 ――公益社団法人全日本トラック協会 |
|
2025.08.18 |
▶冠水路の危険性や道路冠水時における車両の走行性能について動画で解説 ――一般社団法人日本自動車連盟 |
|
2025.08.04 |
▶電動キックボードを見かける人の 約8割が電動キックボードの走行に危険を感じたことがある ――株式会社ウェブクルー 株式会社ウェブクルーは、週に3日以上車を運転し、電動キックボードを見かけた経験のある5大都市(札幌市・東京23区・名古屋市・大阪市・福岡市)在住の男女1、088名に、電動キックボードに関する意識調査を実施しました。
車の運転中に車道を走行する電動キックボードを見かける頻度を聞いたところ、「週に数回見かける」が最も多く31・1%となり、次いで「ほぼ毎日見かける」が22・3%と続いています。
「電動キックボードを見かける」を選んだ人に、電動キックボードの走行を見てヒヤリとしたり危険を感じたりした経験の有無を尋ねたところ、「何度もある」が58・0%、「一度だけある」が19・3%という回答となり、合わせて77・3%の人が電動キックボードの走行にヒヤリとしたり、危険を感じたりしたことがあるとわかりました。
電動キックボードの運転者がどのような行動をしたときにヒヤリとしたり危険を感じたりしたか聞いたところ(複数回答)、「車の間をすり抜けて走行していた」が最も多く69・1%となり、次いで「歩道や路地から急に飛び出してきた」が53・4%、「信号を無視して走っていた」が48・6%と続いています。
また、車の運転をする際に電動キックボードと安全に共存するために心がけていることを聞いたところ(複数回答)、「電動キックボードとの間隔を十分にとる」が最も多く、72・7%となりました。
詳しくは下記URLよりご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000391.000002830.html
出典:自動車ドライバーから見た電動キックボードに関する意識調査(株式会社ウェブクルー)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000391.000002830.html
:ズバット 車買取比較(株式会社ウェブクルー)
https://www.zba.jp/car-kaitori/cont/column-20250701/
|
|
2025.07.28 |
▶整備不良で最も多いのは「空気圧不足 ――一般社団法人日本自動車タイヤ協会 |
|
2025.07.22 |
▶「事業用自動車事故調査委員会10年総括」を公表 ――国土交通省 |
|
2025.07.04 |
▶大雨・台風接近時は出発前に最新情報をご確認ください ――NEXCO3社 |
|
2025.06.30 |
▶過労死等防止対策セミナー資料を公開 ――公益社団法人全日本トラック協会 (公)全日本トラック協会では、各都道府県トラック協会において、「過労死等防止対策セミナー~健康起因事故の削減を目指して~」を開催しています。
このセミナーでは、過労死等や健康起因事故の現状を知り、運転者が健康であるために管理者がどのように運転者に生活習慣の改善等を促すかという手法を学ぶとともに、小集団による意見交換を通じて自社の取組みレベルを把握し、他社の健康管理に関する取組みの好事例などから新たな気づきを得ることによって事業者の取組みを促し、過労死等の防止および健康起因事故の削減を図っています。
今般、(公)全日本トラック協会のホームページに、このセミナーで使用している資料が公開されました(一部はセミナー受講者限定)。
(公)全日本トラック協会は、セミナーを受講した事業者が自社の運転者の健康意識の向上および生活習慣改善のための教育教材として活用すること、またセミナー未受講の事業者が運転者の健康管理の取組みに役立てるよう、呼び掛けています。
詳しい内容は、下記のURLにてご確認ください。
https://jta.or.jp/member/rodo/karoushi_seminar.html
出典:「過労死等防止対策セミナー資料の公開について」(公益社団法人全日本トラック協会)
https://jta.or.jp/member/rodo/karoushi_seminar.html
|
|
2025.06.25 |
▶「ゾーン30プラス」の整備計画を新たに71地区で策定 ――国土交通省 「ゾーン30プラス」は、最高速度30km/hの区域規制と狭さくやハンプなどの物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする施策のことで、国土交通省と警察庁の連携のもと令和3年から取組みを開始しています。
警察と道路管理者は地域の交通安全への課題や地域住民との合意形成等を踏まえ、歩行者等の通行を最優先とした対策内容や、関係機関による取組みの推進体制等を記載した「整備計画」を策定のうえ、都道府県警察本部および地方整備局等に報告し、「ゾーン30プラス」として取組みを進めています。
新たに71地区で「整備計画」が策定され、全国263地区で「ゾーン30プラス」に取り組んでいます。
国土交通省では、「ゾーン30プラス」の取組みを進める地区への技術支援や道路管理者への財政支援を行い、人優先の安全・安心な通行空間整備のさらなる推進を目指すとしています。
詳しい内容は、下記のURLにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001948.html
出典:「生活道路の交通安全施策「ゾーン30 プラス」の追加について
~新たに71 地区で整備計画が策定されました~」(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001948.html
|
|
2025.06.10 |
▶車と自転車の交通ルールを巡る対立意識調査を実施 ――イーデザイン損害保険株式会社 警察庁の発表によると、交通事故全体に占める自転車関連事故の割合は過去10年間で増加傾向にあります。また、令和2年~令和6年の自転車関連の死亡・重傷事故の約8割が自動車との事故となっています。
こうしたなかで、自動車と自転車のどちらが悪いのかという論争がSNS上で起きていることを踏まえ、イーデザイン損害保険株式会社は、週に1回以上車に乗る人250名と週に1回以上自転車に乗る人250名を対象に「車と自転車の交通ルールを巡る対立意識調査」を実施しました。
はじめに、自転車側に対して、「車に危険・迷惑だと思われるのに、ついやってしまう運転」について質問したところ、「交通量にあわせて、車道と歩道を交互に移動しながら運転する」が50・8%で最多となりました。その理由としては、「交通量の多い車道が怖い」「車が停車していて歩道しか通れないときがある」などの声が挙がりました。
次に、車側と自転車側それぞれに対して相手にやめて欲しいと思う運転について尋ねると、車側では「左右や後ろを確認せずに走路を変更すること」「スマホを触りながらの運転」「自転車が二台並んでの走行はやめて欲しい。二台以上で走行する際は一列に並んで欲しい」といった意見がみられました。一方、自転車側では「幅寄せしてくる運転はやめて欲しい」「横断歩道で止まらないこと」「路上駐車で自転車走行帯を塞ぐこと」などの意見が挙がりました。
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000022908.html |
|
2025.06.02 |
▶外国人向けの『バス運転者を目指す人の為の学習用テキスト』を公開 ――公益社団法人日本バス協会 |
|
2025.05.26 |
▶「衝突被害軽減ブレーキ」の不要作動時の対処方法動画を公表 ーー国土交通省 国土交通省は、「衝突被害軽減ブレーキ」の不要作動時の対処方法動画を公表しました。
前方の障害物に対する運転者のブレーキ操作をサポートする「衝突被害軽減ブレーキ」は、カメラやレーダーなどの技術の進化により、追突等の事故が約6割減少するといったデータもあり、高い安全効果が期待されています。しかし、システムの特性や機能には限界があり、使用する環境や条件によっては、意図しない場面で作動(不要作動)することがあるため、この動画を活用して「衝突被害軽減ブレーキ」への理解を深めましょう。
●衝突被害軽減ブレーキとは
衝突被害軽減ブレーキは、車両のカメラやレーダーなどの検知装置により、衝突のおそれがある場合、警報によって運転者にブレーキ操作を促し、運転者がブレーキ操作をしない場合は、緊急的に自動でブレーキを作動させる装置。
●システムの不要作動と対処方法
稀に衝突の可能性が高くないと考えられる状況でも、使用する環境や条件が重なることによって、衝突被害軽減ブレーキが不要作動する場合があります。
予期せぬ作動に慌てず対処するため、取扱説明書を読み、システムの特性や作動条件等を正しく理解して使用してください。
①急なブレーキがかかるおそれがあるので、シートベルトを着用しましょう。トラックでは、普段から荷物を固縛しましょう。
②システムが作動し車両が停止した後に、車両が動き出さないように、慌てずブレーキを踏むようにしましょう。
③カメラ前方のフロントガラスを清掃する等、システムが適切に作動するようにしましょう。
出典:運転支援システムの特性や限界を知ってみよう!
~ 「衝突被害軽減ブレーキ」の不要作動に慌てないためのビデオを公表します ~(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_005420.html |
|
2025.05.19 |
▶「道路データプラットフォーム」を公開 ーー国土交通省 国土交通省は、xROAD(クロスロード)の一環として、道路に関する基礎的なデータを一元的に集約し、幅広く提供する「道路データプラットフォーム」を公開しました。
※xROADとは...・・・データ利活用等により道路調査・維持管理等の高度化・効率化を図る道路システムのDXの取組
道路データプラットフォームの公開によって、これまで道路管理者で共有されていた交通量やETC2.0の速度データが誰でも活用できるようになりました。
なお、同省は今後も活用可能なデータを増やしていく等、道路データプラットフォームの充実を図っていくとしています。
●道路データプラットフォームの機能
・ポータルサイト(URL:https://www.xroad.mlit.go.jp/)
データの概要を閲覧できるリンク、連携するAPI仕様書等を確認できる、道路関係の情報を知る入口となるカタログサイト
・道路データビューア(URL:https://view.xroad.mlit.go.jp/)
各データを一元的に表示し、また地図上で重ね合わせられるWEBマップ
<閲覧可能なデータ例>
① 交通量データ:全国約2、600箇所(機械観測された直轄国道の方向別交通量データのうち、一定の精度が確保されている箇所)で観測される交通量を最速30分前からリアルタイム公開
② ETC2.0の平均旅行速度データ:全国の道路約20万キロ(幅員5.5m 以上の道路で都道府県道及び指定市の一般市道も含む)の平均旅行速度が毎月更新され最長1年分公開
●道路データプラットフォームの活用方法の例
①平日や休日のお出かけの際に、どこで渋滞が発生しやすいかの確認
②交通量と道路構造物の点検結果を重ね合わせ、優先的に修繕する箇所の検討
③人気観光地へのアクセスルートにおいて、直近の交通状況をもとにした数時間先の渋滞予測
④スマートシティ関連のダッシュボードと連携した、都市全体のリアルタイムの交通状況の可視化
出典:「道路データプラットフォーム」を公開します
~xROAD(クロスロード)の一環として、道路関係のデータを集約、幅広く活用可能に!~(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001931.html |
|
2025.05.12 |
▶「事業用トラックの交通事故ゼロを目指す日」が制定される ――公益社団法人全日本トラック協会 |
|
2025.05.07 |
▶同乗者がいると、高齢運転者による事故のリスクが低下する可能性あり ――公益財団法人交通事故総合分析センター等 国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京大学、公益財団法人交通事故総合分析センターの共同研究グループは、2014年から2020年までに全国で発生した交通事故のデータをもとに、高齢運転者の事故を起こすリスクが同乗者の有無によって異なるかを検討しました。その結果、認知機能が低下した高齢運転者であっても、同乗者がいると事故を起こしにくい可能性があることがわかりました。
本研究では、2014年から2017年までに認知機能検査を受検し、運転免許を更新した75歳以上の免許保有者のうち、免許更新後3年間に車両相互事故に遭った運転者の認知機能検査の結果と交通事故のデータを組み合わせ、事故時の運転者を第1当事者(過失の重い方、約10万9、000人)と第2当事者(事故時に法令違反がなく無過失であったと考えられる方、約5万7、000人)に分けて、事故時の同乗者の有無を認知機能検査の結果ごと(認知症のおそれがある人、認知機能低下のおそれがある人、いずれのおそれもない人の3群)に男女別で比較しました。
分析の結果、男女とも、認知機能検査の結果にかかわらず、第1当事者(男性:15~16%、女性:10~11%)より第2当事者(男性:29~33%、女性:26~27%)のほうが同乗者を伴っているケースが多くなりました。
一方、二者間で事故の発生に寄与しうる要因(年齢、過去の事故経験、事故時の時間帯・天候・場所)に大きな違いはみられませんでした。
この結果は、認知機能検査で認知症や認知機能低下のおそれがあると判定された高齢運転者でも、同乗者がいれば、車両相互事故で第1当事者になりにくい可能性を示唆しています。
詳しい内容は以下のURLよりご確認ください。
https://www.itarda.or.jp/top/164/show_pdf.pdf |
|
2025.04.28 |
国土交通省は、近年の共同住宅への配送需要の増加等に伴う荷さばき駐車施設の不足や車種毎の駐車施設の需給の偏り、車両の大型化等に対応するため、地方公共団体が条例を作成する際に参考としている「標準駐車場条例」を改正しました。
◆改正の概要
【量的課題への対応】
①共同住宅への荷さばき駐車施設附置の義務化
一定規模(50戸等)以上の共同住宅に対し、戸数に応じて(100戸あたり1台等)荷さばき駐車施設の設置を義務づける
②公共交通利用促進措置による緩和
交通施策と連携した場合の附置義務の緩和による駐車場供給の適切化
③駐車施設の振替規定の追加
車両規格の多様化への対応や自動二輪車等の駐車施設の確保
④附置義務緩和についての規定の追加
専用駐車場について、敷地内の需要が十分賄える場合の緩和
⑤廃止時の届出義務化
施設の廃止に伴い廃止された附置義務駐車施設の把握
【質的課題への対応】
①荷さばき駐車施設の車高への対応
原則3・2mとする
②車椅子使用者駐車施設の数・車高への対応
駐車施設の規模に応じた基準(バリアフリー法に基づく政省令の改正と連動)の見直しと車高の規定を2・3mとする
③集約駐車場への隔地の推進
バリアフリー法に基づく政省令の改正と連動置義務駐車施設の集約を可能にする規定を導入することで、歩行者の安全性向上やまちの賑わいに影響の大きい建物1階部分の活用を推進
④駐車施設の振替規定の追加
車両の大型化(ハイルーフ)等に伴う駐車需要への対応
◆スケジュール
令和7年3月28日 改正標準駐車場条例及び技術的助言の通知
令和8年4月1日 駐車場法施行令の施行※
※これまで特定用途ではなかった共同住宅を特定用途に追加。地方公共団体の条例により共同住宅に対して附置義務制度の対象とできる地域が拡大
出典:標準駐車場条例」を改正
~社会の変化に対応した駐車施設の附置義務制度の見直しを推進~(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000119.html |
|
2025.04.21 |
国土交通省は、整備工場に車を持ち込むのではなく、自動車整備士に自宅や自社に来てもらいたいというニーズを踏まえて訪問特定整備制度を新設しました。
従来は、エンジンやブレーキ等の取外しなど安全上重要な整備である「特定整備」は、国の認証を受けた整備工場である「認証工場」が、その事業場内で行う必要がありました。
しかし、今回の訪問特定整備制度の新設により、安全を担保する一定のルールの下、認証工場がユーザーの自宅や運送会社の作業場など事業場外の場所を訪問して特定整備を行うことが可能となりました。
たとえば、自宅で車のエンジンがかからないときに整備士に来てもらい、修理を受けることや、人手不足のために自社の整備工場を維持できなくなった運送事業者等に認証工場から整備士を派遣して整備を行うことが可能となります。
◆訪問特定整備制度の主なポイント
①認証を受けた自動車整備工場(認証工場)でのみ訪問特定整備を行うことが可能
②ユーザー等から委託された特定整備を他の訪問特定整備事業者に行わせることはできない
③訪問特定整備の責任は、訪問する整備士ではなく認証工場が負う
④訪問特定整備制度には、訪問特定整備と限定訪問特定整備の2種類がある
●訪問特定整備
・場所 認証工場の設備要件を満たす場所(例:運送会社の整備作業場等)
・作業範囲 すべての特定整備
●限定訪問特定整備
・場所 認証工場の設備要件を満たさないが安全・品質を確保できる場所(例:ユーザーの自宅駐車場等)
・作業範囲
①ブレーキパッドの交換
②発電機交換
③スターターモーターの交換
④大特車のステアリングホースの交換
◆スケジュール
公布 令和7年3月31日
施行 令和7年6月30日
出典:自動車の「訪問特定整備」制度を新設します(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000336.html |
|
2025.04.14 |
▶歩行中の交通事故死傷者数で最も多い年齢は7歳 岡山トヨペットがPR動画を作成 ――岡山トヨペット株式会社 岡山トヨペット株式会社は、同社が取り組んでいる交通事故ZEROプロジェクトとして、PR動画「cap&bear」を公開しました。2020年から2024年における歩行中の交通事故死傷者数(出典:警察庁・令和7年)で最も多い年齢が7歳であることを踏まえて、PR動画のテーマは「魔の7歳」としています。
7歳は小学校に入学する年齢であり、一人で行動する機会が増えます。こどもは大人の予測を超えた行動をとることが多いうえに、こどもの視野は大人の約3分の2ほどしかなく、周囲の状況を把握しづらくなっています。そのほか、こどもの身長が低いため、ドライバーから見えにくい場合もあります。これらのことから、7歳は歩行中の交通事故リスクが最も高い年齢であり、「魔の7歳」と呼ばれています。
また、同社が全国の18歳以上の男女300人に「歩行中の交通事故死傷者数で最も多いのは7歳」であることを知っているか尋ねたところ、93・7%が「知らない」と回答しました。また、小学生のこどもを持つ親300人に対して、同じ質問をしたところ、「知らない」が50・7%となり小学生の親であっても半数以上がその事実を知らないことが明らかになりました。
詳しい内容は以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000061397.html |
|
2025.04.08 |
▶一般道路の後席シートベルト着用率は45・5% ーー警察庁・JAF 警察庁とJAFは合同で「シートベルト着用状況全国調査」を実施し、その結果を公表しました。
運転席の着用率は、一般道路で99・2%、高速道路等で99・6%、助手席においてもそれぞれ95%を超える着用率となりました。
一方、後部座席のシートベルト着用率は、一般道路では45・5%、高速道路等で79・7%と、2002年の合同調査開始以来、過去最高となりましたが、前の座席と比べて着用率が低い状態で推移しています。
●警察における今後の対策
・全ての座席におけるシートベルト着用の徹底を図るため、衝突実験映像等を活用するなどして、着用の有効性・被害軽減効果を実感できる交通安全教育の推進
※特に、後部座席におけるシートベルト着用について、関係機関・団体等と連携した着用義務の周知
・交通指導取締りの推進
出典:シートベルトの着用状況について(警察庁・JAF)
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250204001.html |
|
2025.03.31 |
▶安全運転に関わる脳活動と視覚行動の相関を解明する研究成果を発表 ――株式会社アラヤ 株式会社アラヤは、株式会社本田技術研究所と共同で、MRI対応運転シミュレーターを用いて安全運転に関わる脳活動と視覚行動の相関を解明する研究を実施しました。
本研究に用いたシミュレーターは、実車同様のハンドルやペダル操作が可能で、さらに運転中の視線の動きも同時に計測することができます。
実験では、自車に衝突するリスクがある他の車両(以下、リスク車両)に対する運転者の反応を観察しました。具体的には、右側のサイドミラーに映るリスク車両をどのように視覚的に認識し、それに対してどのようなブレーキ操作を行うのかを調べました。同時に、そのときの脳の活動を詳細に記録し、安全運転に必要な脳の働きを分析しました。
主な研究成果は以下の通りです。
①「安全運転ができていた急ブレーキが少ない運転者ほど、リスク車両を見た時間を合計するとトータルで長い時間注目していた」という関連が明らかになり、これらの運転者では状況の言語的・空間的な理解に関わる脳の領域(上側頭溝前部・上前頭回)と適切な運転行動の選択に関わる脳の領域(前部帯状回)の活動が高くなっていることがわかった。
②「安全運転ができていた参加者ほどリスク車両に最後まで視線を向けている」という関連が明らかになり、これらの運転者では他の車両の運転者の視点に立って行動を予測することや、運転行動の決定に関わる脳の領域(側頭頭頂接合部)の活動が高くなっていることがわかった。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000049573.html |
|
2025.03.24 |
▶通学路の交通安全対策を促進するため「モデル地域」を65か所選定 ――国土交通省 国土交通省は、通学路における交通安全の取組みを推進するため、小学校等周辺において面的な交通安全対策を促進する「モデル地域」を全国で65か所選定しました。
「モデル地域」では、道路管理者が警察や学校・教育委員会、PTA等と連携・協力して、小学校等周辺区域における通学路上の事故や交通規制、自動車走行速度などのデータを活用して交通安全上の課題を分析し、対策内容の検討や地域との合意形成を進め、「ゾーン30プラス」の導入などによる通学路の面的な交通安全対策を実施します。
「モデル地域」の取組みに関しては、データ活用にあたり国土交通省よりETC2・0プローブデータ等を活用した分析などの技術的支援を実施するとともに、「ゾーン30プラス」整備にあたり国庫補助等による財政的支援を実施します。
今後、「モデル地域」の取組みから得られた知見を活用し、「モデル地域」以外の地域においても通学路の面的な交通安全対策を推進していく予定です。
詳しい内容は下記URLにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001898.html |
|
2025.03.17 |
▶令和6年中の交通事故発生状況 65歳以上の死者が平成27年以来の増加 ――警察庁 警察庁が発表した「令和6年における交通事故の発生状況について」から、全体および65歳以上の交通事故の発生状況の推移を紹介します。
令和6年中の交通事故による死者数は2、663人(前年比15人、0・6%減)、重傷者数は2万7、285人(同351人、1・3%減)でした。
死者数を状態別でみると、歩行中が965人(全死者数に占める構成率36・2%)、自動車乗車中が876人(同32・9%)、二輪車乗車中が487人(同18・3%)、自転車乗用中が327人(同12・3%)、特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)乗車中が1人(同0%)となりました。昨年と比べると「自動車乗車中」は増加しましたが、「歩行中」「二輪車乗車中」「自転車乗用中」は減少しました(特定原付は、状態別死者数としては令和6年より集計開始)。
65歳以上の死者数は1、513人(前年比47人、3・2%増)で、全死者数の56・8%を占めています。また、65歳以上の死者数は、平成27以降は毎年減少していましたが、令和6年は増加に転じました。
※状態別死者数の「全死者に占める構成率」は、小数点以下第2位を四捨五入している。
出典:令和6年における交通事故の発生状況について (警察庁)
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R06bunseki.pdf |
|
2025.03.10 |
▶乗用車・貨物車ともに 半数近くの車両がタイヤ整備不良 一一般社団法人日本自動車タイヤ協会 今回は、一般社団法人日本自動車タイヤ協会が発表した、2024年1~12月に全国で39回実施した路上タイヤ点検の結果を抜粋して紹介します。
■実測によるタイヤ点検結果では半数近くにタイヤ整備不良あり
タイヤ点検を行った車両数は、高速道路(自動車専用道路含む)が221台、一般道路が885台の計1、106台で、このうち、高速道路が190台、一般道路が156台の計346台に実測によるタイヤ点検を行いました。
実測によるタイヤ点検の結果、タイヤ整備不良率は、高速道路が36・8%、一般道路が64・7%、全体で49・4%となりました。
■最も多い整備不良項目は「空気圧不足」
タイヤの整備状況を項目別にみると、高速道路、一般道路ともに、「空気圧不足」の不良率が最も多くなりました(高速道路:33・2%、一般道路:58・3%)。
車両グループ別にみると、整備不良率は「乗用車」が48・9%、「貨物車」が53・3%、「特種車」が100%、全体で49・4%となりました。
出典:「2024年「タイヤ点検結果」の報告」一般社団法人日本自動車タイヤ協会
https://www.jatma.or.jp/docs/news_psd/news1282.pdf |
|
2025.03.03 |
▶トラック・物流Gメンの「集中監視月間」に 432件の法的措置を実施 ――国土交通省 国土交通省では、令和6年11・12月をトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を強化しました。
トラック事業者への「違反原因行為実態調査」やトラック・物流Gメンによる関係省庁と連携したヒアリング等によって入手した情報に基づき、423件の「働きかけ」(荷主304件、元請事業者104件、その他15件)および7件の「要請」(荷主4件、元請2件、その他1件)を実施し、違反原因行為の早急な是正を促しました。
さらに、過去に「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた2社(荷主1社、倉庫・利用運送事業者1社)について、当該荷主等が要請後もなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認め、当該荷主等に対し違反原因行為をしないよう「勧告」し、その旨を公表しました。
今回、「勧告」「要請」等の対象となった荷主等に対しては、改善計画の提出も指示しました。今後の取組状況等については、トラック・物流Gメンによるヒアリングや現地訪問等を通じてフォローアップを行い、「要請」後も改善が図られず違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、「勧告・公表」を含む厳正な対応を実施するとしています。
出典:「トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について」国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000319.html |
|
2025.02.25 |
▶企業における社用車の導入と管理・運用の実態に関する調査結果を公表 ――パイオニア株式会社 パイオニア株式会社は、企業で車両管理に関わる業務経験のある人300名を対象に、社用車の購入から検討、運用管理に至るまでの実態に関するアンケート調査を実施し、レポートを公開しました。調査結果の一部を抜粋して紹介します。
はじめに、社用車導入時の実態と検討ポイントに関してみていきます。社用車を購入する際の車種については、小型自動車や軽自動車が主流となっており、平均購入価格は、「150万円から250万円未満」が最も多くなりました。
社用車導入時に重視されているのは初期費用やランニングコストなどで、入れ替えサイクルは「5年」が最も多く、オートリース契約・車検の満了時や社内規定に沿った形で計画的に実施していることがわかりました。
次に、社用車管理で利用しているサービスやシステムをみると、法人ガソリンカードや駐車場カードの利用率が高くなっています。
また、社用車の約7割がカーナビやドライブレコーダーなどの安全装置を装着しています。
管理業務では「アルコールチェックアプリ」の利用率が最も高くなりました。
最後に、社用車管理の課題と改善施策をみると、「現場からの車両不具合・修理・メンテナンスに関する問い合わせ」が管理者の最大の負担となっていることがわかりました。
今後改善したいことについては、「契約・保険の見直し」、「カーシェアの導入・レンタカーの利用」などが挙がりました。コスト面以外では、「現場ドライバーの業務効率化」や「事故削減」への関心が高くなっています。
詳しい内容は以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000935.000005670.html |
|
2025.02.17 |
▶交通事故発生件数、負傷者数、死者数のいずれも前年より減少 ――警察庁 警察庁が「令和6年中の交通事故死者数について」を発表しました。
令和6年における交通事故発生件数は290、792件(前年比17、138件減、5・6%減)、負傷者数は343、756人(前年比21、839人減、6・0%減)、死者数は2、663人(前年比15人減、0・6%減)でいずれも減少しています。
死者数における高齢者の割合は全体の56・8%(1、513人)で、前年と比較して増加しています。
月別交通事故死者数は、12月が287人と最も多く、次いで10月(252人)、11月(248人)となっています。なお、各月を前年同月と比較すると、3月(177人)は21・7%減少となりましたが、6月(198人)は12・5%増加しました。
出典:「令和6年中の交通事故死者数について」(警察庁)
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250107001jiko.html |
|
2025.02.10 |
▶EVトラック・バスへの識別表示義務等について ――国土交通省 国土交通省は令和7年1月10日に道路運送車両の保安基準等の一部を改正しました。
EVトラック・バスの普及が進みつつあるなか、これらの車両で事故が発生した場合にはディーゼル車とは異なる消防・救助活動が必要とされます。このことから、EVトラック・バスを対象として、外観から電気自動車であることを識別できるよう、段階的に新車にEV専用のラベルを表示するよう義務付けました。
また、乗用車と同様、二輪自動車等においても電子制御による先進安全装置の装備が進んでおり、不正なアクセスを受けるリスクが高まってきていることから、二輪自動車等を対象として段階的に新車にサイバーセキュリティに関する基準を適用します。
●改正の概要
①バスおよび車両総重量3・5トン超の トラックのうち、高電圧にて作動する 原動機を備える自動車の前部および左 右側面(バスは後部を含む)には、次 のラベルを表示することとする
【主な要件】
・幅:110mm以上
・高さ:80mm以上
・配置および記号は、ISO17840 -4:2018に準拠
【適用時期】
・新型車:令和8年9月1日
・継続生産車:令和9年9月1日
②二輪自動車、側車付二輪自動車および 三輪自動車にサイバーセキュリティ対 策を求める
【適用時期】
・新型車:令和11年7月1日
・継続生産車:令和13年7月1日
詳しい内容は以下のURLにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000319.html |
|
2025.02.03 |
▶最長の距離を運転した際、 休憩を取りながら運転した人は約8割 ――株式会社NEXER 今回は、株式会社NEXERと株式会社アートフレンドAUTOが、全国の車の運転をする男女500名を対象に行った「長距離運転」についてのアンケートを抜粋して紹介します。
■長距離運転で
■最もキツかったことは眠気
一度に最長でどれくらいの距離を運転したか聞いたところ、「501km以上」が最も多く30・2%となりました。長距離運転で最もキツかったことを尋ねたところ、「眠気」が41・2%で最多となりました。
■約4割が長距離運転にあたって
■準備したもの・ことがある
最長の距離を運転した際、休憩を取りながら運転したか質問したところ、82・6%が休憩を取ったと回答し、その理由には「休憩を入れないと危険だから」などが挙げられました。
また、42・0%の人が長距離運転にあたって準備したこと・ものがあると回答しました。準備したものとしては、渋滞にハマったときに備えた携帯トイレや、眠気覚ましのコーヒーやガム等が挙げられました。
出典:「長距離運転に関する調査」(株式会社NEXER/株式会社アートフレンドAUTO)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001434.000044800.html
株式会社アートフレンドAUTO https://artfriend-auto.co.jp/
|
|
2025.01.27 |
▶7割以上が、自転車罰則強化に賛成 ――おやこじてんしゃプロジェクトby OGK おやこじてんしゃプロジェクトby OGKは段階的に強化されている自転車の罰則について全国の保護者へアンケートを実施し、結果を公開しました。
はじめに、自転車取り締まり強化について聞いたところ、子ども乗せ自転車を利用前の保護者(大賛成:36・2%、どちらかといえば賛成:43・8%)、利用中の保護者(大賛成:21・6%、どちらかといえば賛成:52・0%)ともに7割以上が賛成と回答しました。
次に、自転車の青切符導入についての理解度を聞いてみると、「なんとなく」が子ども乗せ自転車を利用前の保護者(36・3%)、利用中の保護者(36・7%)ともに最も多い回答となりました。
また、子ども乗せ自転車を利用中の保護者に、これまでにヒヤリハット経験があるかを聞いたところ、「被害者側の経験あり」が36・9%と最も多く、次いで、「自損や物損経験あり(28・8%)」、「危ない思いをしたことはない(21・4%)」となりました。
出典:自転車罰則強化アンケート調査レポートを公開! 80%の保護者が『賛成』と回答(おやこじてんしゃプロジェクトby OGK)https://www.atpress.ne.jp/news/421338 |
|
2025.01.20 |
▶運転技術のうち「縦列駐車」が 自信がない人が最も多い ――ソニー損害保険株式会社 ソニー損害保険株式会社が、2004年4月2日~2005年4月1日生まれの1、000名を対象に実施した「2025年 20歳のカーライフ意識調査」から、「免許保有」と「運転技術に対する自信」について抜粋して紹介します。
●免許保有している人は約半数
普通自動車運転免許を持っているか聞いたところ、「普通自動車免許を持っている(オートマ限定)」は40・6%、「普通自動車免許を持っている(マニュアル)」は12・9%で、合計した『運転免許保有率』は53・5%となりました。過去の調査結果と比べると、2023年61・2%、2024年56・2%と、2年連続で下降しました。
また、「現在、教習所へ通っている(オートマ限定)」は3・4%、「現在、教習所へ通っている(マニュアル)」は1・8%、「時期は決まっていないが、取得予定」は23・1%で、合計した『運転免許取得予定』は28・3%でした。
●自信がある人が最も多い運転技術は 「交差点での右折」
運転免許保有者535名に、「車庫入れ」「縦列駐車」「交差点での右折」「高速道路への合流」の4つの運転技術についてどのくらい自信があるか聞いたところ、「自信がある(「とても自身がある」「やや自信がある」の合計)という回答が最も多かったのは、「交差点での右折」(61・3%)で、次いで「高速道路への合流」(41・5%)となりました。一方で、「自信がない(「全く自信がない」「あまり自信がない」の合計)」という回答が最も多かったのは、「縦列駐車」(70・5%)で、次いで「車庫入れ」(65・2%)と続いています。
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2025/01/20250107.html
出典:ソニー損害保険株式会社 https://www.sonysonpo.co.jp/auto |
|
2025.01.14 |
▶渋滞時は「音楽を楽しむ」ことでリラックスする人が最多 ――株式会社R&G 株式会社R&Gは、社会人の男女498人を対象に「渋滞時の車内に関する意識調査」を実施しました。
渋滞が「とても嫌い」「やや嫌い」と答えた人は、合わせて87・4%でした。嫌いな理由を聞いたところ(複数回答)、「予定が狂う」と答えた人が127人で最も多く、次いで「時間がもったいない」で101人でした。
一方で、「渋滞が嫌いではない」と回答した人に理由を聞くと(複数回答)、「のんびりできる」(11人)、「仕方ない」(10人)などが挙げられました。
また、渋滞時の車内でリラックスして過ごす工夫を質問したところ(複数回答)、「音楽を楽しむ」と回答した人が362人で最も多く、全体の7割以上を占めました。次いで、「おしゃべりする」(52人)、「お菓子をつまむ」(51人)が続いています。 詳しくは以下のURLにてご確認ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000144554.html
出典:株式会社R&G https://r-andg.jp/ |
|
2025.01.06 |
▶8割以上が、運転時に人を乗せていると「緊張感がある」 ――株式会社NEXER 株式会社NEXERと株式会社トランスアクトは「普段車を運転する」と回答した全国の男女500名を対象に、「人を乗せて運転するときに注意していること」についてのアンケートを行い、結果を公開しました。
はじめに、自分以外の人を乗せるときに、安全運転をより心がけるなど意識していることはあるか聞いたところ、85・8%が「ある」と回答しました。具体的には、「ゆっくりブレーキを踏む」、「スピードを出しすぎない、カーブのときもよりゆるやかにできるように気をつけている」などが挙げられました。
次に、1人のときよりも人を乗せているときの方が緊張感があるか聞いたところ、「とてもある」、「ややある」と回答した人が82・6%となり、緊張する最も大きな要因は、「同乗者への責任感(85・5%)」でした。具体的な回答理由としては、「ケガさせるわけにはいかないから」、「人の命を預かり運転しているということを意識している」などが挙げられました。
出典:【普段車を運転する500人に調査】82.6%が、運転時に人を乗せていると「緊張感がある」
株式会社NEXER https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001435.000044800.html
株式会社トランスアクト https://transact.co.jp/ |
|